|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
コフキコガネ
(コガネムシのなかま) |
|
ナガサキアゲハ
(チョウのなかま) |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
発見日 H20年6月27日
発見者 2年3組 男子3名,女子3名
コガネムシのなかまです。粉を体全体にくっつけている(こをふいている)ように見えることからこの名前がつきました。夜に電灯によく飛んできます。 |
|
発見日 H20年6月30日
発見者 6年2組 男子1名
アゲハチョウのなかまです。黒っぽいチョウで,クロアゲハににていますが,羽の根元に赤いもようがあるのでわかります。長崎(ながさき)住んでいた「シーボルト」という人が最初に採集したことからこの名前がつきました。 |
|
|
|
|
|
|
|
コクワガタ(オス)
(クワガタムシのなかま) |
|
ナミテントウ(さなぎ)
(テントウムシのなかま) |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
発見日 H20年6月27日
発見者 柳原先生
大きさ 3.6センチ
クワガタムシのなかまです。クワガタムシの中では見つけやすい方です。大きいものでは5センチくらいになるものもいます。 |
|
発見日 H20年6月3日
発見者 2年1組 男子3名
テントウムシのなかまです。写真はさなぎですが,黒い点のもようがはっきりとわかります。1週間くらいで成虫になり,アブラムシを食べはじめます。 |
|
|
|
|
|
|
|
ノコギリクワガタ(オス)
(クワガタムシのなかま) |
|
キボシカミキリ
(カミキリムシのなかま) |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
発見日 H20年6月25日
発見者 1年男子1名,6年男子1名
クワガタムシのなかまです。オスですが,サイズは小さい方です。クワガタムシやカブトムシは,幼虫の時,栄養がたりないと,成虫になったときサイズが小さくなります。 |
|
発見日 H20年6月23日
発見者 小谷先生
カミキリムシのなかまです。背中に黄色い点(ホシ)があるのでこの名前がつきました。イチジク,ミカンなどの木や葉を食べます。つかむと「キィキィ」となきます。 |
|
|
|
|
|
|
|
クロテンケンモンスズメ(幼虫)
(ガのなかま) |
|
クロカミキリ
(カミキリムシのなかま) |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
発見日 H20年6月24日
発見者 1年1組 男子2名
ガのなかまです。名前の最後に「スズメ」という名前がついていますが,これは羽の色が鳥の「スズメ」ににていることからこの名前がつきました。おしりに針のようなものがついていると,ガの幼虫であることが多いです。 |
|
発見日 H20年6月25日
発見者 1年2組 男子2名,女子1名
カミキリムシのなかまです。マツの木を食べます。集団で生活することが多いため,マツの木がかれることがあります。夜,自動販売機などのあかりによく飛んできます。 |
|
|
|
|
|
|
|
ツ チ イ ナ ゴ
(バッタのなかま) |
|
ムネナガマルガタゴミムシ
(ゴミムシのなかま) |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
発見日 H20年6月17日
発見者 2年3組 男子1名,女子1名
バッタのなかまです。ツチイナゴは成虫で冬をすごすバッタです。写真は成虫なので,寒い冬をのりこえて夏をむかえようとしています。はねをひろげて遠くまで飛ぶことができます。 |
|
発見日 H20年6月17日
発見者 2年3組 女子1名
ゴミムシのなかまです。名前が「ゴミムシ」とついていますが,ゴミによってくるわけではありません。この虫は,キュウリ,ナスなどの野菜の葉などを食べます。 |
|
|
|
|
|
|
|
オオカマキリ(幼虫)
(カマキリのなかま) |
|
コゴモクムシ
(ゴミムシのなかま) |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
発見日 H20年6月17日
発見者 4年3組 女子2名
オオカマキリの幼虫です。オオカマキリは4〜5月ごろ卵から幼虫になり,少しずつ大きくなり,7〜8月に成虫(おとな)になります。写真のようにずいぶん大きくなっていますが,まだ羽は見えません。 |
|
発見日 H20年6月17日
発見者 2年3組 女子1名
ゴミムシのなかまです。「ゴミムシ」のなかまには小さな昆虫を食べるものが多いですが,この虫も,小さな昆虫や麦などのたねを食べます。
|
|
|
|
|
|
|
|
ゴマダラシロエダシャク
(ガのなかま) |
|
ショウリョウバッタ(幼虫)
(バッタのなかま) |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
発見日 H20年6月16日
発見者 2年3組 女子3名
ガのなかまです。幼虫は「シャクトリムシ」とよばれ,のびたりちぢんだりして歩きます。名前の最後が「シャク」になっているガの幼虫はシャクトリムシです。 |
|
発見日 H20年6月17日
発見者 4年1組 男子1名
ショウリョウバッタの幼虫です。6月ごろ卵から幼虫になります。少しずつ大きくなり,8〜9月に成虫(おとな)になります。写真はまだうまれたばかりの幼虫です。 (1センチ) |
|
|
|
|
|
|
|
オオフタモンコメツキ
(コメツキムシのなかま) |
|
ヒ メ ア カ ネ
(トンボのなかま) |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
発見日 H20年6月16日
発見者 4年1組 男子1名
コメツキムシのなかまです。手でつかまえると足をちぢめてしんだふりをします。はねに黒っぽいもんが2つあることからこの名前がつきました。大きさは3センチくらいです。 |
|
発見日 H20年6月16日
発見者 1年2組 男子1名
トンボのなかまです。赤トンボの種類です。成虫になった時はオレンジ色ですが,日にちがたつにつれて,赤くなります。「ヒメ」という名前がついていますが,大きさが小さい昆虫によく使います。 (ヒメコガネ,ヒメカマキリ など) |
|
|
|
|
|
|
|
ラ ミ ー カ ミ キ リ
(カミキリムシのなかま) |
|
ニジュウヤホシテントウ
(テントウムシのなかま) |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
発見日 H20年6月12日
発見者 4年2組 男子2名
カミキリムシのなかまです。イラクサ科の「ラミー」という植物の葉を食べることからこの名前がつきました。ラミーは,くきの部分がじょうぶで水に強いので、網・ロープなどに使われます。 |
|
発見日 H20年5月23日
発見者 1年女子3名,2年女子1名
テントウムシのなかまです。はねにある,ほしの数がだいたい28こあるのでこの名前がつきました。このテントウムシは,アブラムシを食べずにジャガイモなどの葉を食べます。 |
|
|
|
|
|
|
|
オオシオカラトンボ(メス)
(トンボのなかま) |
|
アオスジアゲハ(幼虫)
(チョウのなかま) |
|
|
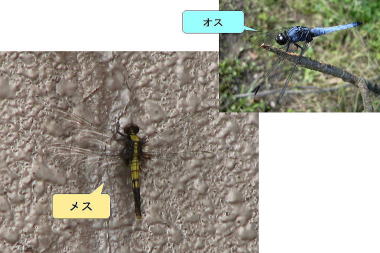 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
発見日 H20年6月7日
発見者 4年女子4名
トンボのなかまです。オスとメスは体の色がちがうのですぐに見わけられます。シオカラトンボににていますが,サイズが大きいことからこの名前がつきました。 |
|
発見日 H20年6月11日
発見者 1年男子1名,2年男子1名
チョウのなかまです。アゲハチョウの幼虫ににていますが,黒いとげのようなものがあります。もう少し大きくなると,とげのようなものはなくなります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Copyright (C) 2008 Municipal Inokuchidai Elementary School in Hiroshima.
All Rights Reserved. |



